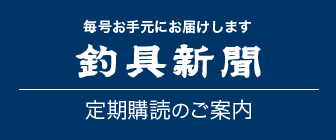各地で釣り場づくりに取り組んでいる岸裕之氏の連載がスタート!
今、日本の内水面の釣り場について、どういう状況なのか、どういった事が問題なのか、どういった取り組みが行われているのか。
内水面の釣りが縮小していると言われて久しいですが、釣具業界にとって、内水面という広大な釣り場が重要である事はもちろん、魅力的な内水面の釣り場を増やす事は、釣り界の将来にとっても非常に重要です。
内水面の釣り場について問題点を整理し、素晴らしい釣り場を増やす一助になればという思いで、連載を始めさせて頂きます(釣具新聞編集部)
岸裕之氏のプロフィール
50歳を契機に釣り場づくりの活動を開始。地元の漁業協同組合や観光協会などと一緒に釣りイベントを開催したり、ワカサギ・ヘラブナ・渓流魚などの放流に取り組む。もっと釣り場にかかわる活動がしたくて、2018年の秋に大阪から和歌山県橋本市へ移住。紀ノ川漁協組合員、紀の川河川愛護モニター、貴志川アマゴゾーニング協議会、玉川峡を守る会に所属。2020年春から(公財)日本釣振興会和歌山県支部事務長を務める。1962年生まれ。(有)カモメ通信社代表


釣り場の環境整備は一番重要だが、日本の内水面漁業は窮地に…
釣り具は遊び道具。健全な遊び場がなければ釣り具は売れない。至極当然のことだが、釣具業界にとって一番大切なのは釣り場環境整備であることは言うまでもない。
しかし、日本の内水面漁業は窮地に立たされ、釣り場を管理する漁協運営は厳しさが増すばかり。旧態依然として「放流だけをしていればいい」という漁協は衰退の一途を辿り、漁協組織の解散や、都道府県の内水面漁業協同組合連合会から脱会する漁協も後を絶たない。
さまざまな問題に直面する日本の内水面漁業に未来はあるのか。今号からスタートするこの連載は、内水面のフィールドをリサーチする企画だ。

- アイデアを絞り出し、釣り人の誘致に成功している釣り場
- 画期的な水産資源の保護増殖事業(調査研究も含む)
- 漁業関係者と釣り界(釣り人・業界)との連携事業
この3つを取材テーマとしているが、ひと言でいえば「未来につながる釣り場環境整備」の紹介である。
釣具新聞に掲載をお願いしたのは、業界人にもっと漁業の現場を知ってもらい、漁業関係者と釣り界が協働で釣り場環境整備に取り組む機会を増やす必要性を感じたからだ。
日本の内水面漁場は、都道府県の知事から第五種共同漁業権免許を与えられた漁業協同組合が管理しているケースがほとんどだ。
その漁協の活動を釣り界がこれまで以上にサポートしなければならない時代になったといえるだろう。
好環境の釣り場管理は漁協、釣り人、釣具業界の共通の課題。
(公財)日本釣振興会や(一社)日本釣用品工業会でも釣り場環境整備に力を注いでいるが、漁業者や有識者、自治体の水産関係者との距離はまだまだ遠いように思える。

では、内水面の釣り場ではどのような問題があるのか、具体的に見ていきたい。
・釣り人、内水面漁業の従事者とも高齢化が深刻
釣り人、内水面漁業の従事者ともに高齢化は切実な問題だ。
私の地元、和歌山県はアユ釣りのメッカだが、アユ釣り人口は平成6―8年をピークに現在は3分の1まで落ち込み、60歳以上が60%と高齢化が進んでいる。


手軽に楽しめるワカサギ釣りや、ゲームフィッシングの要素を取り入れた渓流釣り場のように、ファミリー層や観光客、ルアーフィッシングファンを誘致できない釣りジャンルは、あと数年でさらに厳しい局面を迎えることが予想される。
現にヘラブナ管理釣り場はこの十数年の間に廃業する施設が増え、釣りファン減少に拍車をかけている。
そして、釣り人以上に深刻なのが漁業従事者の高齢化と人材不足だ。
これまで内水面漁業をリードしてきたアユやヘラブナ釣りは熱いコアファンが多い一方で漁場管理のランニングコストが高く、遊漁料収入の低下と種苗価格の高騰は漁協経営を圧迫している。放流だけに頼っているアユ釣り河川のほとんどが赤字運営となっている。
・内水面漁業の活性化には外来魚の活用が不可欠という現実
外来魚といえばブラックバスを連想する人も多いだろうが、2005年の外来生物法施行後は徐々にそのカテゴリー分けや対策が進んでいる。
内水面漁業の切り札的な存在であるニジマスに関しては侵略的外来種に指定する国がある一方で、我が国では古くからゲームフィッシュとして活用されてきた経緯から「産業管理外来種」として位置づけられている。

ただ、第五種漁業権免許のない釣り場ではニジマスを活用できないケースもある。
80年代はさまざまな外来種の移入と養殖で内水面漁業の生産性を高める施策がとられてきたが、90年代に入ると「保全生態学」が内水面漁業にも影響が及ぼすようになり、遺伝子レベルの種の保存が善で、生態系に影響を与える外来種は悪という有識者の見解が広まってきた。
「国内外来種」というカテゴリーに分類される湖産アユやヘラブナ、ワカサギなどの放流も問題視する見解が聞かれるようになり、原種のアマゴを守るためにDNAが異なるアマゴの放流を認めないエリアもある。
種の保全はとても大切なことではあるが、内水面漁業の活性化には外来魚の活用が不可欠な現実がある。
種の保全と漁業振興の両方を推し進めるにはもはや保護水域と、漁場(釣り場)を分けて考えるしか解決策はないだろう。将来を見据えたゾーニング管理はまだまだ話合いが必要だ。
・天然資源の活用と調査研究費不足
漁協運営を立て直す上で重要視されるのが釣り対象魚の自然再生産性の向上や、効率のよい保護増殖方法の導入だろう。
ワカサギの増殖は自然繁殖+人工孵化で費用対効果が高く、この魚の増殖に取り組む漁協が増えるのも頷ける。
海産遡上アユに恵まれた河川は冷水病にも強く、放流だけに頼っている河川と比較すると資源管理ではかなり優位だ。


ただ、日本は長年の間、放流を中心とした事業を行ってきたため、漁場の調査研究という面では残念ながら先進国とはいえない。海なし県の奈良県は釣り場環境に恵まれながらも内水面試験場等の公的な研究機関はなく、アユの養魚施設もない。
アメリカやオーストラリアのように州政府がしっかりと漁場管理計画を立てている国と比べるとその施策に遅れをとっている。
また、水産資源の管理において、古い漁業調整規則が妨げになっているケースもある。記者の地元、和歌山県の漁業調整規則に定められた採捕制限は、マス類(ニジマス・アマゴ)10㎝以下。しかも制限匹数が設けられていない。
渓流魚の増殖においても、条件が揃えば歩留まり率が高いという調査結果が出ている発眼卵放流や親魚放流が未だに義務放流として扱ってもらえない地域が多い。
釣りファンの減少傾向が続くことを仮定すると、自然の恵みを活用することは内水面漁業の最後の砦と言えるかもしれない。
(第1回・了)
取材協力・情報提供のお願い
この連載企画の取材を通して画期的な釣り場づくりに取り組んでいる方々や、調査研究で成果を上げている方々とお会いできることをとても楽しみにしています。これからの1年、読者の方々と一緒に未来の漁場管理の在り方を考えるコーナーを作るべく、現場を回って取材する所存です。読者の地元で「この釣り場の活動は素晴らしい」といった情報があれば、本紙編集部 mail@tsurigu-np.jp までご一報いただければ幸いです。
よろしくお願い致します(岸裕之)。
関連記事 → 【第2回】やるぞ内水面漁業活性化事業、第二期へ。未来の漁協運営モデルを創出
関連記事 → 【第3回】アユルアーで新たな友釣りファン作り。釣り場次第で新たなゲームフィッシングも誕生か!?
関連記事 → 【第4回】遊漁券もネット販売の時代!?
関連記事 → 【第5回】増加するブラックバスの有効利用。各地でバス釣り人の受け入れ態勢が充実
関連記事 → 【第6回】滋賀県安曇川廣瀬漁協に見る漁場管理者のプロ意識~これからの時代の漁場管理と釣り人へのサービス考察~