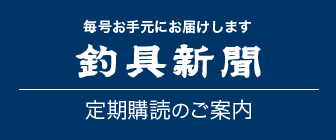遊漁券の未購入者は25%。釣り人のモラル向上は急務
内水面の釣りには水産資源保護法、都道府県が定める漁業調整規則、内水面漁場管理委員会の指示、第五種共同漁業権免許を受けて漁場を管理する漁協が定める遊漁規則など、とにかく規則が多い。
禁漁区や禁漁期に釣りをする悪質な釣り人は絶えない。そして、遊漁券を購入しない釣り人はまだまだ多いという。
中村智幸氏のアンケート調査によると、遊漁券の未購入者は全体の25%。これはアンケートに答えた自主申告の数字なので実際にはもっと多いという。地域によっては50%近い未購入者がいるのではないかと問題提起されていた。言わずもがな漁協の収入減に直結する大きな問題である。
今回のウエブセミナーで「青森県の内水面漁協における貧困さと危機感」というテーマで漁協運営の現状を報告した同県内水面漁業協同組合連合会の古内由美子氏からも、遊漁券の未購入者が多いということが問題視されていた。
青森県の場合、渓流釣りは日券が400~500円、県の指導で現場加算金は1.5倍までと定められている。もともとの料金設定が低いため1.5倍といっても400円から600円と200円程度加算されるだけなので、漁協によってはほぼ釣り人は遊漁券を購入しないで釣りをするという報告があった。
実際に遊漁券を購入する場所がないケースが渓流釣りの場合に多い。その解決策として期待されているのが電子遊漁券販売システムの導入だ。
関連記事 → 【第4回】遊漁券もネット販売の時代!? 内水面の釣り場はどう変わるのか
関連記事 → 【第14回】3年目の「やるぞ内水面漁業活性化事業」電子遊漁券販売システム導入中心に30事業を補助
令和3年度やるぞ内水面漁業活性化事業ではICT導入(電子遊漁券システム)に特に力を入れ、その経費の二分の一を補助する制度を打ち出した。結果、令和3年度だけでも全国の38漁協がICT導入で同事業の採択を受けた。
今後、電子遊漁券の普及でどこまで購入率が高まるのか。また、このシステムが普及することによって釣り人の行動データが得られ、どのように漁場管理に活かされるかも楽しみだ。
話は内水面の釣り規則に戻るが、いかに規則が守られるかは釣り人のモラルの問題である。釣り人のマナー、モラルの向上に取り組むことは釣り界、特に釣りメディアが大きな役割を担っているのではないだろうか。