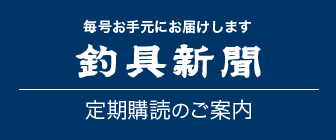カワチブナ(ヘラブナ)のルーツ

文献によると、『明治38年~39年頃、中河内郡瓢箪山(現在の東大阪市) の養魚家橋本福松氏が淀川で捕獲した体高の高いゲンゴロウブナと、八尾市在住の田坪房吉氏が宇治・ 巨椋池で飼育していた体高が高いゲンゴロウブナとを交配させ、これを原種として人工淘汰し、 体高が高く大きく成長するフナに創りあげたのが現在のヘラブナである。
その後、大阪の河内地方で食用魚として盛んに養殖されるようになったのは大正10年頃の話であり、 昭和17年、河内地方に淡水養魚組合が結成された時に特産の「カワチブナ」として命名された』。
※1986年初版発行・江藤江舟著『ヘラブナ』(西東社刊)より引用
また、長年ヘラブナの研究を続けてきた大阪府水生生物センター(現・大阪府立環境農林水産総合研究所生物多様性センター)のホームページには次のように紹介されていた。
カワチブナ(ヘラブナ)はゲンゴロウブナから作りだされた養殖品種である。明治末ごろに河内の人が淀川や巨椋池で採取した体高が高いフナを選び選抜淘汰を重ねてきた大阪府の特産魚である。
カワチブナのルーツは、かつて存在した巨椋池(おぐらいけ)
河内地方で養殖されたカワチブナのルーツは巨椋池(おぐらいけ)とされている。巨椋池は京都伏見の南側、ちょうど宇治川、桂川、木津川の淀川三川が合流する地点にあった巨大な遊水地だ。
淀川水系は流域面積が広く、流量が多いため、巨椋池は下流域の洪水被害を軽減する大きな役割を果たしていた。
ゲンゴロウブナは琵琶湖にも生息するが、巨椋池は琵琶湖よりも水温が高くて富栄養化が進み、大きく育ったと言われている。また、河内からだと遠くの琵琶湖へ行く必要もなかった。
残念なのは、巨椋池は干拓が進むにつれて規模を縮小し、昭和の初期に消滅したこと。周囲が16㎞ほどあった遊水地は、季節によってその大きさや形を変化させ、水生動物の宝庫であり、漁業が盛んに行われてきた記録が残っている。
ヘラブナは食用から釣り対象魚へ
河内地方でのヘラブナの養殖はまだ巨椋池が残存していた明治時代から始まった。
山口養魚場は明治40年に創業し、ヘラブナ養殖とともに歩んできた。
創業者の時代は食用魚として生産したが、二代目の時代に釣り用としても扱われるようになる。当初は農業が中心の兼業だった。
そして、現社長の山口裕二郎氏の父、三代目社長の時代となり、関東への出荷が増え、釣り対象魚としての需要が急速に高まる。現在も米、野菜、ハスの花などの栽培も継続しているが、ヘラブナの生産が山口養魚場の主力の業種となっている。
全国各地にフナを食する文化が残っているが、東大阪にもウロコのままフナを焼き、昆布巻きにする伝統料理があり、祭りのときに振る舞われる。
◆山口養魚場について

山口養魚場の五代目社長となる山口裕二郎氏(左)と、先代(四代目)社長の山口裕之(ひろじ)氏。
若社長の裕二郎氏は昭和63年生まれの33歳。大学を卒業した2011年から就業し、裕之氏は叔父にあたる。父が三代目社長を務めていた。
裕之氏は昭和31年生まれの65歳。ヘラブナ養殖に携わって43年のキャリアを誇り、まだまだ現役。各地の放流現場へも出向く。
次ページ → 新たな愛好者獲得へ。ヘラブナ釣り再興策とは?