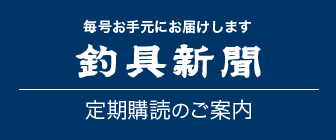水辺の自然と触れ合う石干見体験

世界の多くの地域で有史以前から行われてきた人類最古の漁具、漁法とも言われる石干見(いしひび)。
干潟に石垣を築き、潮の満ち引きを利用して魚介類を採捕するその古来の漁を体験するイベントが行われた。
場所は海老江地区で、淀川大橋(国道2号線)の左岸下流側だ。
主催は竹門先生が代表を務める「京の川の恵みを活かす会」で、大阪市漁協の協力のもと、JOFI奈良やヒューマンフィッシングカレッジの先生や学生、日本釣振興会のメンバーも応援に駆け付けた。
竹門先生は市民、特に子どもたちに淀川の生き物や河川環境に興味を持ってもらえればとこのイベントを企画。「万博のときに世界各地から大阪にやってくる子どもたちにも石干見漁を体験してもらう」という構想も温めている。
かつて高度成長期の日本がそうであったように、大切な自然を失いかけている発展途上国は少なくはない。万博へ向けて自然と融合した大都市をPRすることで、水都大阪の魅力がさらに高まりそうだ。
◇第1回・6月26日:石垣づくり作業
地元の小中学校が実施している海遊館連携授業にもこの石干見漁体験が組み込まれ、初回は60名の子どもたちや大阪市職員も含め、総勢80名が参加。河川敷にある石を利用して石垣づくりに励んだ。

魚は潮が満ちてくると摂餌場となる浅瀬へ移動し、石垣よりも岸側に入り込む。石垣には引き潮時に魚が沖へ移動できるように魚道(出口)を開けておいた。

第1回目の作業は石垣を積み上げたところで終了。石裏や潮だまりにはさまざまな生物が生息し、その多さに驚く参加者も多かった。
◇第2回・7月24日:漁網設置と漁獲
石垣を築いて1カ月後の大潮の日に、魚が沖へ移動する時の魚道を塞ぐように漁網を設置し、潮が引き切るのを待った。

まだまだ石垣に隙間も多く、高さもないため心配されたが、見ごとハゼ類(マハゼ・ウロハゼ・ヌマチチブ)などが網に入っていた。大成功である。

より高く隙間をなくすように石垣を積み上げれば、スズキやクロダイなどの大型魚の捕獲もできそうで、漁獲量は増えていきそうだ。
毎年少しずつ石を積み増し、石垣を立派に育てていくことも石干見漁の楽しみで、夏から秋の淀川の恒例イベントになりそうだ。
8月に予定していた第3回は大水が出て中止になったが、今後は石干見で漁獲した食材で調理にもチャレンジしていく。
次ページ → 淀川舟運が水都大阪の新たなシンボルに…!25年の大阪万博へ向けて