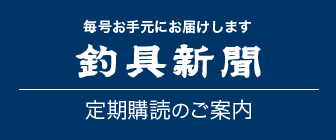アカハタは本州から九州、それらの南岸に位置する離島にかけての岩礁地帯やサンゴ礁で多く見られる高級魚です。水深2mから160mにかけて生息し、私的な感覚になりますが、カサゴよりも水深と潮通しの良い場所の海底近くで良く釣れるように感じます。産卵期は主に夏場で、クロダイとは逆で、雌から雄に性転換することも知られています。
根魚の人気は昔からあり、まず衰えることは無いと思いますが、体色の鮮やかなアカハタは、食味も見た目も良いので、たとえその日の本命では無くても釣れると、とても嬉しいお魚さんの1種です。
近年は栽培漁業の成果や温暖化の影響があるのでしょうか、磯釣りに行った時に昔よりも良く釣れるようになった気がします。そうした事もあってか、最近はゴロタや堤防からの専用のロッドも市販されるようになりました。情報を調べるとやはり生息域は北に広がっているということです。
条件が揃えば比較的簡単に狙うことが出来るターゲットなので、今後さらに広がっていくことが予想されます。
ワームやメタルジグに好反応。サザエの赤身の置きっぱなしも良く食べてくる!?
アカハタは魚の切り身などをエサにしたブッコミ釣りで狙うほかに、ワームやメタルジグにも良く食って来ます。疑似餌で釣りをされる方から見るなら、アカハタを効率よく釣るためには、リーリングやロッドアクションによる誘いが重要だと思われるかもしれませんが、意外なことに石鯛釣りで使用しているエサ取りが食べ残したサザエの赤身を何も誘わず置きっぱなしの状態でも良く食って来ます。
もっとも釣り人にしてみれば、エサと仕掛けを竿掛けにセットしたまま置いてあるので、誘いが無いように思えるかもしれませんが、サザエの赤身は楕円形で平たい形状をしているため、潮流があれば思いのほか動きが出ていることでしょう。
しかしながら海中に暫く放置したサザエの赤身は大変身が硬くて、指でちぎることが出来ないほどの強度があります。
また興味深いことに、根魚を釣る場合、1―2尾釣れたらこまめに場所を変えてキャストした方が効率は良いのですが、アカハタに関しては同じ場所に投入した仕掛けに対して、5―6尾、時にはそれ以上の数が釣れることがあります。
くわえた獲物が逃げにくい歯の形状
ではアカハタはどのようなプロセスでエサを発見し、捕食するのでしょうか。
アカハタの歯は鋭くとがった小さな歯が顎の骨に並んでいて、2―4列になっています。前回お話ししたラージマウスバスやスズキの歯と似た形状をしていて、くわえた獲物が逃げることが出来ないようにしっかりとグリップするのに適した形状です。

体の割には口が大きい根魚独特の形態をしていますが、歯を構成している顎全体の作りはブリやスズキにも似ていることから、短距離であればかなりのスピードで突進し一気に口に入れるというパターンです。
ここで短距離と言っていますが、歯を含めた顎の骨全体はそれほど重量が無く、クロダイのように頑丈な作りではないものの、体に対して相対的に口が大きいため、長距離に渡って獲物を追尾することは不向きと考えられます。
ハタやカサゴの仲間は視覚が優れていて、接近してくる獲物を素早く発見し、射程距離まで近づいてきたらすかさず突進して口に入れます。
嗅板は複雑な構造。匂い成分も有効と思われる
一方、同じポジションで複数が釣れることから、ある程度嗅覚も発達しているのではないかと思いますが、アカハタの嗅板を観察すると思いのほか複雑な構造をしています。
石鯛釣りのように同じ場所に繰り返し餌を投入することによって、投入された餌から溶出する匂い成分に対しても反応し徐々に集まってくることが推測されます。

アカハタはアタリが明確なため、投入後にラインが弛んでしまっても竿先が大きく動きます。またアワセが遅れてしまっても飲み込んだままその場所に留まっていることが多いので、焦る必要もありません。
ただし注意点としては、やはり根の周囲で食ってくるお魚さんであるため、アタリが来ているのに放置するなどすると、仕掛けごと根に持ち込まれることがあるのでNGです。
チョイ投げで誘いをかける釣りは、お魚さんの視覚に餌のありかをアピールする上で大変有効な手段であることに違いはありませんが、起伏の激しい岩礁地帯の海底を狙う釣りにおいて、頻繁に誘いをかけることは根掛かりを誘発する頻度も高くなります。

そんなことから臭いを発する餌、扁平になっていて弱い潮流でも動く餌、こんな餌を使用して、ここぞと思うポイントでじっくり待つのも、手軽に釣る良い方法かもしれません。
長岡寛の記事 → 長岡寛 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト
関連記事 → サバは美味な食材?それとも外道?サバの習性や種類について詳しく解説。食中毒にも気を付けて! | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト