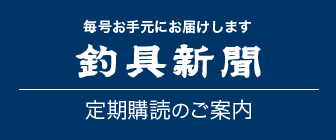公益財団法人日本釣振興会は、小学生及び教員などを対象に、身近な海や川、湖沼の魚族資源や水辺環境等への興味関心の醸成や、水辺でのルール・マナー・安全対策等の啓発を通じ、青少年の健全な成長、社会の発展に貢献することを目的に「釣りを通じた環境学習(以下、釣り環境学習)」を小学校の正規の授業として推進している。
アユの放流やアオリイカの産卵床製作、釣り調査など多彩なフィールドワーク

2021年度から始まった「釣り環境学習」は今期で4年目。今年は東京都でも初開催され、7月末時点で東久留米市、横浜市、三浦市の3地域、6校で座学やフィールドワークを実施している。
実施校は東久留米市立本村小学校、東久留米市立第五小学校、川崎市平間小学校、横浜市立幸ケ谷小学校、横浜市立篠原小学校、三浦市立名向小学校。学年は1年生、3年生、4年生、5年生、6年生と学校により様々だ。
座学の講師陣も多様で釣具メーカー社員、漁業協同組合組合員、出版社経営者、日本釣振興会事務局職員等が担当している。


フィールドワークも様々なテーマで展開しており、ライフジャケットの着用による安全教育はもちろん、アユの放流やアオリイカの産卵床製作、手長エビ釣り、クチボソ釣り等、開催校の身近な水辺を活用し、リアルな体験の場を提供している。




秋以降も、各地の小学校で釣り環境学習を計画
子供達からは「いろいろな種類の魚がいることを知り、釣りに興味がわきました」、「良い海だと思っていましたがゴミなどがあることを知り、どうしたらいいか考えたいです」、「釣りや魚をつかまえる大変さがわかりました」、「身近な生き物にふれあえたのでとても嬉しかったです」などといった感想が寄せられている。
日本釣振興会では、夏休み以降も各地の小学校などで釣り環境学習を推進していく計画だ。
問い合わせ先は、(公財)日本釣振興会釣り環境学習担当・吉野(TEL 03-3555-3232)まで。
【提供:日本釣振興会・編集:釣具新聞】