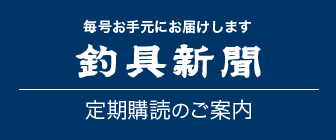キジハタ(アコウ)の生産はまだ増える見込み
大阪で力を入れているキジハタの生産はこれからまだ増えていくと思います。キジハタの生産は非常に難しいのですが、だからこそ高級魚なのです。親魚の飼育も大変ですし、受精率を高める工夫や水深のある水槽など様々な設備とノウハウが必要です。ヒラメやマダイのように養殖の技術が確立されている魚種ではありません。令和元年では、大阪府のキジハタの種苗生産は20万尾、放流は10万尾(サイズは80㎜)行っています。
そして、資源量もまだ少ないと思います。放流が過剰に行われ、その魚が増えすぎると魚体が小さくなり、他の生態系にも影響が出ると言われていますが、今はそのようなデータはありませんから、まだまだキジハタは放流できると考えています。

小さなキジハタが釣れたら、ぜひリリースを!
キジハタなどハタ類は成長が非常に遅い魚です。40㎝を超える大物ならば、確実に10年以上は生きている魚です。ですから、釣り人の皆様も、小さいキジハタが釣れたら、ぜひ逃がしてあげて欲しいと思います。数年後に大きくなって、また現れてくれると思います」
近年、北海道や東北はもちろん、各地でロックフィッシュゲームとしてもキジハタは人気のターゲットだ。こうなった背景には、栽培漁業センターの活動の成果があると思われる。魚族資源の増加は、釣り人もその恩恵を受けている。
そもそも栽培漁業は瀬戸内海で始められた!
そもそも、こういった栽培漁業は瀬戸内海で始められたという。最後にその経緯を伺った。
「栽培漁業は1960年代に瀬戸内海で始まりました。当時は高度経済成長期でもあり、沿岸が一斉に埋め立てられました。魚が住み、卵を産む浅場の多くが陸地になり、さらに工場排水や生活排水の影響もあり、水質も悪化し魚族資源も減少し、漁業者の生活も困窮したと言います。そこで瀬戸内の府県が集まり水産庁に陳情を行い、モデル海域として瀬戸内で栽培漁業が始まりました。
それまで、養殖業はあったのですが、漁師の間でも、一旦育てた魚を一般海域に離すといった発想はありませんでした。しかし、瀬戸内海を1つの湾として放流を続け、ある程度成果が出ると、栽培漁業の考え方も定着していきました。そして、全国にもこの栽培漁業の活動は広がっていきました。栽培漁業は魚族資源の拡大に間違いなく貢献していると考えています」
栽培漁業は概ね5年間のスパンで実行される。各都道府県で、5年間でどの魚種をどの程度放流するのかといった計画が事前に立てられ、実行されているそうだ。そのため、釣り関係者が「特定の魚種の稚魚が欲しい」と要望しても受けられない場合もある。また、飼育している魚種でも、放流できるサイズまでどの程度の割合で育つのかは、年によって異なる。そのため、稚魚の入手が容易な場合とそうでない場合もあるそうだ。
取材協力:大阪府栽培漁業センター → http://www.osaka-gyogyoukikin.jp/saibai/
関連記事 → 「年なしのチヌ」って本当は何歳?クロダイ(チヌ)の全ての解明を目指す、広島大学の海野徹也教授を取材
関連記事 → 【海野徹也】魚に愛、自然に感謝、釣り人に幸。「初期減耗と種苗放流」~魚たちは実に厳しい世界を生き抜いている~
関連記事 → 【海野徹也】魚に愛、自然に感謝、釣り人に幸。~放流先進国の日本。原動力は世界に誇る種苗生産技術!~
関連記事 → 【海野徹也】魚に愛、自然に感謝、釣り人に幸。~種苗放流の実績と動向~