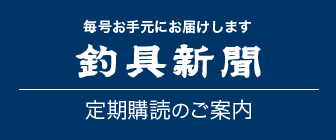ベテラン釣り記者の竹村勝則(たけむらかつのり)氏が「昔と今の釣り」について思うままに語る、「釣り記者の回顧録」。
今回は、昭和の時代に竹村さんが体験した友釣りと、その変遷について語ってもらいました。

竿は軽く、糸は細く…。何十年もかけて変化してきたアユ釣りの世界
アユ釣りの世界は変わりました。
昔は重い和竿の3間、4間だったのが、今はカーボン竿で長いものはなんと12mもあり、主流は8.5mから9m竿で、重量はわずか200g前後です。片手でも楽々操作できます。
竿だけでなく、糸はナイロンの0.6号、1号を使っていたのが、今の水中糸の細いものはメタルでは0.01号と見えないほど細い。
竿と糸はおそらく世界一の軽さと細さの世界一づくしで、私たちはアユ釣りをしているのです。
これはアユ釣り師の要望と、それに応えてくれた釣りメーカーのたゆまぬ努力と技術力のたまものです。しかし、ここに至るまでは何十年もかかっています。
九州では「目通し」仕掛け!? 昔はローカル色が強かった友釣り

私が友釣りを始めたのは50年ほど前です。当時は友釣りの参考書的なものはなく、見様見真似で、玉川峡(和歌山県)でオトリを泳がせていました。
瀬ではアユがたくさん見え、アカをはんでいるのもいましたが、簡単には掛かってくれません。
そのうちアユがキラキラっともつれるように光り、竿に手応えがきて釣れたのが分かり、無我夢中で取り込みました。
オトリアユを使ってアユを釣るという、他の釣りにはない面白さに魅了されました。
釣り雑誌の編集に携わっていたので、取材がてらあちこちの川へ行きました。
行く川々で、地元の友釣り名人に会いました。急流と尺アユで知られる九州の球磨川では、地元のアユ釣り名人・塚本昭司氏の鼻カンのかわりに、縫い針で目を刺してくくる「目通し」仕掛けには目を見張りました。
昭和の中期の釣りは、まだローカル色が強く、友釣りの基本はかわらずとも、釣り方、仕掛けなど各地独特なものがありました。
現代の友釣りは、引き釣りと泳がせ釣りをミックスした釣法…?

時代とともに友釣りが盛んになり、釣り具メーカーやスポーツ紙のアユ釣り大会が催され、全国の釣り人が参加し、釣り人の交流も盛んで、友釣り釣法は飛躍的に進歩しました。
友釣りは瀬を釣れ、石を釣れとも言うように、瀬に縄張りアユが多くいて、野アユがガツーンと掛かると取り込みはスリル満点です。
アユは瀬にも多いが、小石底のトロ場やチャラ瀬にも多くいます。そのような場所を釣るのに特に適したのが泳がせ釣りです。
泳がせ釣りが大流行したのが昭和53、54年頃からで、知る人ぞ知る大西満名人著「新しい友釣り、泳がせ釣りのすべて」(釣の友社刊)により、全国的に広まったといっても過言ではありません。
今の友釣りは、引き釣りと泳がせ釣りをミックスしたような釣法だと思います。
(了)
竹村勝則氏のプロフィール

竹村勝則(たけむらかつのり)
昭和16年生まれ。
月刊雑誌「釣の友」(釣の友社)編集長を経て、週刊「釣場速報」の編集長(名光通信社)等を歴任。
釣りの記者歴だけでも軽く50年を超え、今でも釣行回数は年間120日以上!
国内で最も古い時代から活躍する釣り記者の1人だ。
関連記事 → アユ釣りは「ドブ釣り」から「友釣り」へ。江戸時代から行われていた!? 気品あふれる釣法【竹村勝則・釣り記者の回顧録】