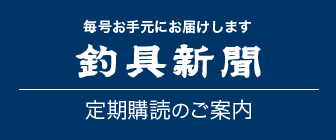我が国の内水面漁業は大きな課題が山積している。その中の1つが川魚の食離れだ。
アユやヤマメ・アマゴ・イワナなどの渓流魚、川魚の大黒柱であるウナギ、琵琶湖のニゴロブナなどの一部の魚種を除けば、食文化における身近な川魚の地位は低下している。
今回は川魚の食文化を継承し、川魚を食材とした新たな調理法や加工品開発に取り組んでいる一般社団法人日本食育者協会の代表理事を務める藤掛進氏と、同会の理事を務め、現在は(株)琵琶湖みらい研究所相談役を務める山根猛氏に話を伺った。

「地産地消、その地域にあるものをどう食べるか」
日本食育者協会は京都市伏見区にある。淀川が舟運で賑わった時代は日本一栄えた港町である。京都といえば桂川、鴨川、宇治川が町中を流れ、何といっても琵琶湖が近い。
そして桂川、宇治川、木津川の三川が合流する地点の南側には、淡水魚介類の宝庫であった巨椋池(おぐらいけ)が広がっていた。
城下町で交通や物流の要所であり、古くから酒造りが盛んで、川魚の食文化が育まれる土壌が揃っていた。
しかし、その京都においても川魚の需要は少なくなってきている。
藤掛氏(昭和27年生まれ)はかつて農産物を取り扱う商社に勤め、農業の視点から食育にかかわるようになった。
ただ、さまざまな改良が進む農産物の生産よりも、ジリジリと衰退する川魚の食文化に危機感を覚えたという。
川魚はもともと資源量が限られ、内水面漁業は産業として成り立ちにくい環境ではあるが、「川の魚は食べられる」ということを若い世代の人たちに伝え、地域に根付いた食文化を残していきたいという。
日本食育協会は納屋町商店街にある食育キッチン石黒(旧屋号は石黒商店)内に事務所を構えている。
この店舗は明治25年(1892年)に雑穀商として創業し、藤掛氏は京都の家庭料理「おばんざい」研究家としてここからさまざまな情報を発信している。
京都の食文化を守りながらも、新しい食のスタイルを提案し続け、子どもたちにもっと川魚や地域の環境に興味を持ってもらえるように「川魚小学校」を開校する構想も温めている。
「漁業従事者の育成、生産者の意識改革も必要」
前職は近畿大学農学部水産学科の教授として教鞭を執っていた山根氏(昭和22年生まれ)は、漁業生産や漁労に精通する。
琵琶湖でさまざまな調査研究を繰り返してきたその経験を活かし、川魚の加工から食べ方、資源管理、若手漁師と共に持続可能な琵琶湖漁業について考えるまで、漁ることから食べることまでのすべてのバランスを考え、将来を見すえた川魚の食文化の再構築に取り組んでいる。
例えば琵琶湖産コアユ、十三湖や宍道湖のシジミにみられるように、ブランド化か進んだ種に関しては特異的に消費が継続する。
ただし、その価値が高まっても漁獲量が限定的(母数が少量)な内水面漁業では収益を伸ばすことは難しいという。
そこで少しでも需要、そして商品価値を高めようと地域特性を活かした水産加工品を次々と開発している。
また、内水面漁業の将来を考えると、漁業の担い手が育たなければ川魚の食文化は途絶えてしまうという。
そこで山根氏は琵琶湖漁業の未来を担う若手生産者数名と協働でさまざまな活動を展開してきている。
そんな山根氏が日本食育者協会とともに最も開発に力を注いできたのがニゴイの新たな活用方法だ。
ニゴイを食べちゃうぞプロジェクト
ニゴイは琵琶湖・淀川水系だけではなく、全国の河川やダム、湖沼に広く生息している。雑食性ながら大型になるほど魚食性が強くなり、貴重な水産資源の天敵にもなりうる。
特にアユ釣り河川では招かざる客である。淡水魚の中では大型の部類に入るが、小骨が多く食材としての需要はほとんどない。そんな未利用魚類の利活用は、ニゴイの繁殖に頭を悩ます河川漁協には朗報かもしれない。
加工の方法に苦労しながらも皮と骨を剥ぐ方法も見つかり、今ではすり身にしてさまざまな加工品が誕生している。
現在はパンなどに塗るパテを2種類商品化し、ニゴイせんべいやマドレーヌなどの菓子作りにもチャレンジしている。