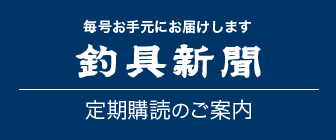公益財団法人 日本釣振興会は10月15日、身近な海や川で水辺環境や魚族への関心を高めてもらうとともに、釣りのルールやマナーを啓発する取り組み「釣りを通じた環境学習」を東京都台東区の区立浅草小学校で実施した。
座学とフィールドワークをセットにした日釣振が推進する青少年健全育成も目的にしたプログラム。当日は4年生が常見会長の講話に耳を傾けるとともに、釣り場で身を守るライフジャケットの正しい着用方法なども学んだ。

浅草小での同環境学習は今回が初めて。ハゼ釣りなども楽しめる隅田川に近い学校という立地もあり、「江戸前と釣り文化の話」を学習テーマに設定しての開催となった。本部が主催し、東京都支部(櫻井孝行支部長)が協力。
当初、フィールドワークとして江戸前の代表的な魚、ハゼ釣りを徒歩5分ほどの言問橋下流隅田川で行う予定だった。しかし、当日の天候や、事前に関係者で実施した試釣りが思わしくなかったため、座学を終えた後の体育館内で、釣りに関する体験へと変更となった。
同小から同環境学習に参加したのは、4年生2クラス51人。体育館に集合した児童たちは、ステージ近くに用意された大型スクリーンの前で、座学に臨んだ。
座学では東京湾の歴史や生息している魚も紹介

講師の常見会長は「今日は釣りの話をします。ぜひ釣りに興味を持ってください」と挨拶。自己紹介後、「江戸前と釣り文化」をテーマに、東京湾や隅田川に生息する魚、湾内での釣り、江戸時代から続く伝統工芸の江戸和竿などについて話した。
常見会長は講話の折々に出問も挟んだ。魚の映像をスクリーンで表示しながら、その名称についての答えも求めた。江戸前で有名なマハゼのほか、東京湾や墨田川で釣れるスズキ、江戸前釣りに欠かせないアナゴなどといった映像がスクリーンに映し出されると、子どもたちは積極的に発言。
常見会長は「江戸前の海、東京湾は多くの魚がいてとても豊か。なぜだか分かりますか」と質問を続け、児童からは思いおもいの返答が。同会長は東京湾には隅田川や江戸川、荒川、多摩川といった複数の河川が流入していることをあげ、「川が多いと、山の方で降った雨や雪が地面から川を通じて東京湾まで流れてきます。川から海へくる間にいろいろな栄養分が東京湾まで流れてきます。栄養分を含んでいるので、たくさんの魚が東京湾にはいるのです」と解説した。
「江戸前」とはもともとどういう意味か知っていますか?
江戸前とは、江戸城の目の前の海のこと。江戸城の前の海だから、江戸前の海。江戸前の釣りでハゼ、アナゴ釣りが知られているが、常見会長は「実は昔、江戸前の釣りでとっても風情があって、有名だった釣りがあります。それは、アオギス釣りです」と紹介。
大正から昭和初期の頃まで盛んに行われていた、このアオギス釣り。だが、東京湾の埋め立てが進捗したことにより、生息数が減少、今ではすっかり姿を消してしまったという。
当時のアオギス釣りのスタイルは独特で、浅い海に3mほどの高さの脚立を立て、釣り人はその上で釣った。
釣りが庶民の間に広まったのは江戸時代。常見会長は、「江戸の人たちは江戸前の釣りをしながら、釣った魚を食べていました。江戸の人たちは、生きていくために釣りをしていたのですね。江戸湾は魚の生息が豊富だったので、釣りにはとても良い環境でした」と説明した。
そんな江戸時代に製作された江戸和竿にも、常見会長は言及。242年前に下谷稲荷町の広徳寺の門前に東作という江戸和竿の店ができたこと、江戸和竿は伝統工芸品であること。さらに、江戸前の釣りは生活のために始まり、次第に文化へと変化していったことなどを、分かりやすく語りかけた。

座学では、ルアーサンプルが会場のテーブルに展示。児童たちは順番にルアーを手にとり、スタッフの説明を受けながら、形状や重量、彩色などを興味深く観察した。
ライジャケの着用方法に加え、キャスティング体験や糸の結び方の講習も
講話後、休憩を挟んでの体育館ではライフジャケットの着用方法やラインの結び方、キャスティング体験がスタート。1部の座学は全2クラス(51人)合同だったが、2部のフィールドワークについては1クラスずつ交代での実施となった。

キャスティング体験は、用意されたスピニングロッドを使って、7―8m先の床に広げられた的に向かってキャストするゲーム感覚のメニュー。
最初、ラインがリールに絡まったり、上方高く飛んでしまったりと操作に苦戦する児童もいたが、何度か投げるうちに扱いもスムーズに。狙った的の上に疑似餌が着地すると、指導したメーカースタッフから「上手、上手!」と称賛の声をかけられ、にっこり。
ラインの結び方教室は、スクリーンに表示された図解を見ながら、太目の糸を使って習得するもの。床面に糸を置き、座り込んで集中して結ぶ子、立ったままの姿勢で手に糸を持って結ぶ子など、熱心に取り組む姿が見られた。

日本釣振興会の「釣りを通じた環境学習」は、2021年から開始され、総合学習として学校の開催希望は年々増加。
これまで、神奈川県横浜市、同川崎市、同逗子市、同三浦市、埼玉県桶川市、東京都久留米市などで実施されている。
導入した学校からは、「担任だけではとてもできない豊かな経験をさせていただいた」「地元の海でフィールドワークをする価値は掛け替えのないこと。子どもたちも大変喜んでいた」などといった感想が寄せられている。【小島満也】
関連記事 → 小学生が東京湾でカサゴの稚魚放流。座学で環境や水辺の安全も学ぶ。日本釣振興会の「釣りを通じた環境学習」開催 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト
関連記事 → 日本釣振興会が行う「釣りを通じた環境学習」。釣りも活用して地域の環境、水辺の安全対策等を教える。東京・本村小学校の授業を紹介 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト