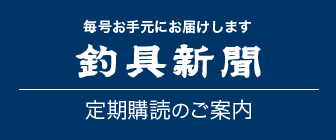お魚さんは味と臭いに敏感で大変なグルメであることは、幾度かお話しさせて頂きました。また、言うまでも無くお魚さんを釣るための釣り餌は、釣れたお魚さんを食べる場合、間接的に人体に取り込まれることになります。
そればかりではなく、釣れたお魚さんをリリースする場合でも、使用する釣り餌はお魚さんが食べることになり、やがて環境に放出されることになるため、釣りに使う餌はお魚さんや人体に対して、また可能な限り自然環境に与えるインパクトが小さくなるように設計の段階から工夫していく必要があります。
そのため釣り餌メーカーでは、原料となる素材について相当な努力を重ねて今日に至っているのです。
つまり、釣り餌の原料のほとんどは、お魚さんや人が(間接的に)食べても健康への悪影響が無い、もしくは極めて少ない物のみが使用されています。
一方、自然界では分解しにくいプラスチックやメタルが素材となっている疑似餌は釣りの最中、根掛かりなどによって意図的では無くても自然界に取り残されてしまうケースもあります。
不幸にして水中に取り残されてしまったそれらの疑似餌は何らかの形で回収しない限り、長期に渡り環境中に取り残されてしまうことになります。
これら全てを回収することは大変困難なことではありますが、(公財)日本釣振興会では、釣り場の保全や美化運動を推進していて、その中の清掃活動においては、これらの回収事業も展開しています。
タンパク含量によって成長や食いつきに雲泥の差
さて、話を戻すと、釣り餌の原料は安全性が重要と言うことになりますが、私がメーカーに入社して数年が経過した頃はまだ本格的な研究設備が整っていませんでした。
そんな中で、数多くある原料の性質を把握するため、それぞれのタンパク含量を調べることにしました。
養魚飼料は言うに及ばず、釣り餌もタンパク含量によってお魚さんの成長にも食いつきに雲泥の差が出ます。

その理由は、お魚さんが好むアミノ酸はタンパク質を構成する化学物質で(一部例外もあります)、タンパク含量の多い原材料には、それらアミノ酸も多く含まれています。そのタンパク含量(租タンパク)を調べる方法の1つに、ケルダール法という実験手法があります。
ケルダール法の由来は1883年にその手法を発見したデンマークの科学者の名前から来ていて、150年以上経った現在でも用いられている分析手法です。
この原理は、硫酸と試料を混合して加熱することにより、タンパク質に含まれる窒素が硫酸アンモニウムという化学物質に変化します。
それを滴定して中和し(アンモニアもタンパク質も窒素を含んでいるという共通点があるので)、そのアンモニア量として換算することにより、タンパク含量が算出されるというものです。試料を分解するための硫酸と言うのは、濃硫酸を指しています。
ある日のこと、硫酸を用いて実験をしているとそれを見た別の社員が、「なぜ釣り餌に硫酸が必用なのか?」と怪訝な面持ちで私に尋ねてきました。
私は、今ここに記載した内容を大雑把に説明しましたが、なかなか納得してくれる様子はありませんでした。それもそのはず、硫酸は誰もが知っている通りの劇薬で、万一皮膚に触れるようなことがあればすぐに火傷を負ってしまいます。
しかも、熱いからと、大量の濃硫酸に水を掛けるようなことをすれば、更に発熱して大変なことになってしまいます。
釣り餌の原料である麩やペレットを硫酸が入ったフラスコに入れると、瞬く間にその周囲が黒く焦げたように融解して、独特の強い臭気が漂います。
タンパク含量の測定は今でこそ自動装置が普及したため随分と楽になりましたが、当時はまだ実験器具が乏しい時代でした。反応させるための蒸留装置も、自らガラス管をバーナーで熱して曲げながら作成したことを大変懐かしく思います。
硫酸は容器に注ぐときにも大変な注意が必要であることは言うまでもありませんが、注意深く扱ったつもりでも、僅かな飛沫が衣服に付着するとその部分には簡単に穴が開いてしまいます。
実験する時に白衣を着るようになった理由は…

恥ずかしながら、1回だけ希釈された硫酸を誤って口に吸い込んでしまったことがあります。硫酸は用途によってそれぞれ希釈されたものを用いるのですが、分析実験においては正確に測る必要があります。
ホールピペットと呼ばれるガラス製の計測具で吸い込んで、指で押さえながら滴下させ、目盛り線にピッタリと合わせます。ある時、不注意でボトルに残った硫酸が少なくなっていることに気づかず、ホールピペットで吸い込んでいると、ボトルが空になった瞬間、ホールピペットの先端から空気が侵入して、口の中に硫酸が入ってしまいました。
すると、一瞬にして口の中が痺れた感覚に見舞われました。すぐに大量の水で洗い流しましたが、それでも一週間近く舌が痺れて味覚がありませんでした。以後細心の注意を払うようにしたことは言うまでもありません。
私はこの頃から実験をする時は白衣を着用するようにしました。
釣り餌メーカーの一角に白衣と濃硫酸。当時は誰もが違和感を覚えたことでしょう。しかし、やがて世界初となる味と臭い付きのワームをはじめ数多くのヒット商品が生まれる土台になったのではないかと自負しています。それと共に、あの時口に入れた硫酸の味は今も忘れることはありません。
関連記事 → 長岡寛 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト
関連記事 → 釣果アップのカギ!?フッキングの反射時間と練り餌の強度の関係は?車の運転を例に分かりやすく解説 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト