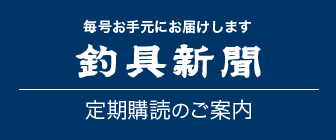河川行政が大きな転機を迎えたのは1997年。この年に河川法が改正され、それまでの治水・利水に加えて、「河川環境の整備と保全」が同法の目的の1つに位置付けられた。
日本のほとんどの河川はダムや堰堤で分断され、都市部はコンクリートで護岸が固められている。人が介在しない自然環境が希少となる中で、国が豊かな水辺環境整備に取り組み始めてちょうど四半世紀が経過した。
苦境に立たされている内水面漁業において、水辺の環境改善と自然再生産による資源の回復は、間違いなく追い風になるだろう。
漁業関係者や釣り人が期待を寄せる河川環境工学は現在、どこまで進歩しているのか。水生生物の視点から魚道研究に取り組む日本大学の安田陽一教授に、これからの日本の河川環境整備について話を伺った。
日本の河川環境はまだまだ改善される!
1997年以降、環境に配慮した河川管理が行われるようになった。
ただ、人の命や生活に直結する治水や利水と比べ、環境改善への取り組みはどうしても優先順位が低くなる。
環境改善には目的や目標があっても、それを達成できなくても罰則があるわけではない。河川法が改正されてからの25年を振り返ると、まだ全国各地の河川で十分に環境改善対策が進んでいるとはいえない。
しかし、全国の河川を駆け巡り、魚道機能の改善に取り組む安田教授は「川に棲む生き物の豊かな生態系を取り戻すことは、長期的な視野で見るととても大切なこと。これからの時代は、治水・利水・環境を縦割に考えるのではなく、土木・環境・水産などの専門家が連携し、それぞれの課題を解決すべくバランスがとれた技術力が求められる」という。
今回、将来へ向けて参考になり得る河川環境土木の事例として、高梁川総合水系環境整備事業を紹介する。
高梁川潮止堰のように環境改善に大きく踏み込んだ事業はまだ極一部だが、このような事業が少しずつ全国の河川に広がり、さまざまなアイデアの効果が実証されることで、さらに河川環境工学のテクノロジーが高まりそうだ。
「日本の河川は治水・利水を目的として整備されてきたため、水生生物が棲む環境面において課題を抱える堰堤や魚道はあまりにも多い。それだけに課題を解決すれば、日本の河川環境は改善の余地がある」と安田教授はいう。
自然の恵みに満ち溢れた豊かな河川が増えることで、内水面の釣りが再び活性化する日を心待ちにしたい。
安田陽一教授のプロフィール

日本大学理工学部土木工学科教授。「川の医者」としてこれまで診断した河川は2000年以降だけでも100カ所を優に超す。
河川環境工学の研究者として、人と水生生物が共存する豊かな河川環境づくりを目指す。栄えあるASCE(アメリカ土木学会)水理学討議論文最高賞を2度受賞。水生生物が遡上・降河できる魚道の設計や改善で多くの命を救う。1963年生まれ。
先進的な潮止堰から見えてくる河川環境の未来【高梁川総合水系環境整備事業(2009~2022年度)】

先進的な堰堤や魚道の構造はどのようなものなのだろうか。
そのモデルになりうる堰を安田陽一教授に伺ったとき、最初に名前が挙がったのが高梁川(たかはしがわ)の潮止堰だった。
高梁川は岡山県の三大水系の一つで、同県西部を南北に流れ、瀬戸内海に注ぐ。その流域面積は2670㎢(広島県を含む)にもおよび、県下最大規模を誇る。
この河川の下流部を管理する国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所から高梁川潮止堰の魚道改良事業(高梁川総合水系環境整備事業)の資料を提供していただき、その概要をまとめた。
この事業は高梁川下流域の自然再生を目的とし、平成21年度(2009年度)に着手し、水生生物が棲みやすい(移動しやすい)豊かな水辺環境を取り戻すために改良を実施してきた。
高梁川潮止堰は大正末期に海水の逆流防止や河川洗掘防止を目的に固定堰として設置されたのがその始まりだ。
今回の魚道改良以前にも魚道は設置されていたが、施設の老朽化とともに、魚道入口を見つけられずに堰の下流部に魚群が溜まる蝟集(いしゅう)が課題であった。
事業には学識経験者(安田陽一教授)がアドバイザーとして参画し、水生生物が移動しやすい構造の魚道が設計された。
川の水量はいつも一定ではない。限られた条件(水量が安定した条件下)しか機能しない魚道が多い中で、改良した魚道は水量の変化に広く対応できることがその特徴だ。
魚たちを迷わせることなく魚道の入口に導き、流れを制御するコンクリートブロックを活用して緩流を創出する工夫が施されている。