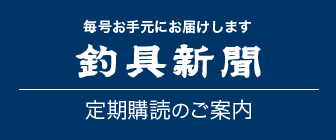ベテラン釣り記者の竹村勝則(たけむらかつのり)氏が「昔と今の釣り」について思うままに語る、「釣り記者の回顧録」。
前回の第2回では、グラスロッドやカーボンロッドができる前に使われていた竹竿について話してもらった。
関連記事 → 【竹村勝則・釣り記者の回顧録】竹の六角投げ釣り竿
第3回では、グレ釣りに使われるウキの変化について語ってもらった。
昔と今でグレ釣り用のウキは大きく変化。水面から水面下へ…

磯釣りほどスリルがあって面白い釣りはない。
上物、底物狙いがあり、昔も今も上物の代表魚はグレ、底物の代表魚はイシダイです。
ウキがゆっくり入るアタリを合わせると、竿をしぼり込むようなグレの強引、豪竿が舞い込む豪快無比なイシダイ釣りにのめり込み、昔も今も離島まで遠征する釣り人は後を絶ちません。それだけ魅力的なのが磯釣りです。
イシダイは荒磯が釣り場となるが、グレは比較的近場の磯でも釣れるので釣り人に人気が高い。
グレ釣りは今も盛んだが、昭和の時代が最も盛んだった。関西方面では四国南西部の磯が次々と開拓され、京阪神からカーフェリーで毎週大勢のグレ釣り師たちが四国へ渡り、大グレを求めて釣行した。
グレ釣りはウキ釣りが主で、その昔は「紀州の棒ウキ、阿波の玉ウキ」とも言われたことがあった。
紀州では潮が比較的ゆるやかな釣り場のせいか、感度がよくて見やすい棒ウキがよく使われていたのではないかと思う。
阿波では、牟岐大島のように潮が比較的速い釣り場のためか、潮に乗りよい玉ウキ(割り玉)が使われたのではと思う。
釣りはローカル色が強いものであったが、時代の流れとともに、釣り人の交流も盛んになり、グレ釣りウキは変化していった。

割り玉の玉ウキは、円錐型になり、中通しウキとなって涙滴型、ドングリ型、丸型など色々な型に変化した。
今のグレ釣りウキは紀州も阿波も、全国的にも玉ウキ系の中通しウキが主流になって釣具店のウキコーナーには何十種類も並んでいる。しかし、タナが深い時は、中通しより、糸の抵抗が少ないカン付きウキがある。
ウキは「浮木」とも書くように、水面に浮かべてアタリを見るものだが、最近のグレ釣りは、ウキは水面ぎりぎりに浮いているか、ウキを沈めていって釣る。
グレのタナを探る場合や、タナが深い場合は遊動ウキ止め糸を使わないイケイケのスルスル釣りで、道糸の動きや竿先にくるアタリを取る。
ウキの浮力表示はBが多いが、0表示は水面ギリギリ、00や000は沈む。さらにウキメーカーによって色々な表示をしている。
昔のグレウキは、水面に浮いていたが、今は水面下にあるといっても過言ではないだろう。
グレ釣りは、釣り方もさることながら、ウキが1番変化、進化したのではないだろうか。
(了)
竹村勝則氏のプロフィール

竹村勝則(たけむらかつのり)
昭和16年生まれ。
月刊雑誌「釣の友」(釣の友社)編集長を経て、週刊「釣場速報」の編集長(名光通信社)等を歴任。
釣りの記者歴だけでも軽く50年を超え、今でも釣行回数は年間120日以上!
国内で最も古い時代から活躍する釣り記者の1人だ。
連載第1回目の記事はコチラ → 【竹村勝則・釣り記者の回顧録】フナに始まりフナに終わる?