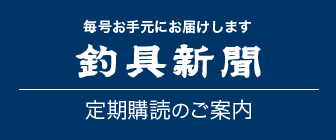「釣具業界の法律相談所」は、釣具業界でも起こる可能性のあるトラブルについて、弁護士の先生に聞いて見解や対処方法を紹介するコーナーです。
今年も記録的な猛暑ですが、今回は熱中症のトラブルです。ぜひ、ご一読を!※質問は架空の質問です。

真夏の恒例釣り大会。大会スタッフとして働いていた外部の業者が熱中症でダウン。後日、訴えてきた
弊社は釣具メーカーです。毎年、夏に釣り大会を開催しているのですが、大会スタッフとして働いていた外部の業者の2名が熱中症になってしまい、後に訴えられるトラブルとなってしまいました。
この外部の業者は、この大会のために弊社が初めて依頼した業者です。大会は毎年恒例で、1年間、練習を積み重ねている選手もいます。毎年大いに盛り上がり、弊社にとっても重要なイベントです。
大会準備は、前日の朝から始まります。大会本部にテントの設置や備品の運搬、ステージの設置などの作業を行います。外部の業者も前日からの作業となります。
大会当日、スタッフは午前5時に現地に集合し、最終の撤収は午後4時頃になる事もあるなど、長丁場の仕事となります。

大会日の日中は、事前の予報通り35℃以上の猛暑となりました。午前8時には30℃を超え、午後6時頃までは30℃以上の厳しい猛暑日となりました。訴えを起こしてきた外部の業者は2名でステージの設置や開会式、閉会式の司会、音響等の仕事を行っていました。
弊社としては、猛暑対策は以前からしっかりと行っていました。冷えたスポーツドリンクや飲料、氷も多めに用意しています。また、塩分の取れる飴、冷たいおしぼりなども多数用意し、いつでもスタッフや外部の業者も利用できるようにしていました。随時、休憩を取るように促していたほか、大会中にスタッフも選手も全員が休憩する時間も設けました。
幸い、大会は無事に終わったのですが、撤収作業の時に外部の業者の1人が「頭が痛くふらふらする」と言ってきました。もう1人の外部の業者も「気持ちが悪い」と座り込んでしまいました。
それぞれ、体調の悪くなった人の体を冷やし、休憩させる事で1人は回復しましたが、もう1人は回復しなかったため、救急車を呼んで病院に搬送する事態となりました。熱中症と診断され、その日は入院となりました。
後日、この2名より「想定外の暑さでの作業となっていた。炎天下に、ステージの運営や、設置や撤収、重い音響の機材の運搬等により体調を崩した。治療費と当面仕事が出来なくなった損害を補償して欲しい」と訴えが起こされました。
そこで弁護士の先生に質問です。
弊社は、熱中症対策は行ってきたつもりです。訴えてきた業者は「想定外の暑さ」と言ってきましたが、夏の屋外のイベントですから、事前に暑くなるのは十分に予測出来たはずです。この業者の訴えを受け入れる必要があるのでしょうか。また、こういった場合、弊社は外部の業者に対しても、熱中症対策についての責任が生じるのでしょうか。
【弁護士の回答】他社の従業員にも「安全配慮義務」として熱中症対策を行う必要がある
本件で、御社は外部業者の作業員2名に対して熱中症対策を行う必要があるのでしょうか。結論から述べると、御社は、外部業者2名についても熱中症にならないように注意する「安全配慮義務」を負っていたといえます。その理由をご説明します。
企業は、自社の従業員だけでなく、他社の従業員に対しても「安全配慮義務」を負うことがあります。このときポイントになるのは、「事業者と外部の作業員が一定の指揮監督関係にあったか」という点です。
こうした関係が認められるのは、作業員に設備や工具などを使用させ、作業上の指揮監督を行っていた場合や(最高裁判所平成3年4月11日判決・三菱重工業事件)、作業員に対して、「保護帽を着用すること」「安全帯を着用し使用すること」といった安全指示をしていた場合など(東京高等裁判所平成30年4月26日判決・日本総合住生活事件)です。
つまり、他社の従業員であっても、企業が作業に使用する道具を提供したり、直接作業を指示したりする関係にある場合、「安全配慮義務」を負うことがあります。裁判所は、こうした関係のことを「特別な社会的接触の関係」と表現します(最高裁判所昭和50年2月25日判決・自衛隊車両整備工場事件)。
本件についてみると、御社は、釣り大会の設営や式の司会、終了後の撤去作業などを業者にさせていたとのことです。そのため、御社が作業員に対して、会場設営のために設備や工具を使わせ、作業工程やスケジュール管理を行うなどしていた場合や、熱中症対策として「水分や塩分の補給をすること」といった指示をしていた場合、「特別な社会的接触の関係にあった」と判断される可能性が高いでしょう。
したがって、御社は、外部業者の作業員2名についても熱中症対策を行う必要があった可能性があります。
「自主的に水分補給しておいてください」では不十分
では、本件では、外部業者に対する安全配慮義務に違反したといえるでしょうか。また安全配慮義務に違反しないためには、熱中症対策として何をすればよいのでしょうか。

まず、従業員が熱中症で死亡し、会社の安全配慮義務違反が問われた裁判例(福岡高等裁判所令和7年2月18日判決・新星興業事件)をご紹介します。
この事案で、裁判所は、行政通達などを参照して、熱中症対策としては「熱中症リスクを適切に評価したか」「十分に睡眠や食事をとっているか確認したか」「水分や塩分などを摂っていない人に、水分などを摂るよう指導したか」が問題になるとしました。
次に、重要な法改正情報をご紹介します。令和7年6月1日、熱中症対策を強化する法改正が行われました(労働安全衛生規則の改正)。これに伴い、事業者は、熱中症のおそれがある場合の報告体制を整えることなどが義務付けられました(労働安全衛生規則612条の2)。
安全配慮義務違反とならないためには、裁判例や法令が求めるのと同等の熱中症対策を行うべきです。御社は、冷えたスポーツドリンクや飲料を用意する、休憩をとるよう促すなどしており、十分な熱中症対策に思えるところです。しかし、裁判所は、それだけでは十分でなかったと判断する可能性があります。
本件では、日中の気温が35℃以上の猛暑日となることが予想されていました。熱中症リスクは高かったといえます。
また、業者の仕事は、大会前日の朝から準備を始め、大会当日も早朝から夕方にかけて日中作業するというハードなものでした。そのため、業者がさらされる「熱ストレス」は相当なものだったと考えられます。
この点、暑くなることが事前に予測できたのであれば、作業員自ら熱中症対策を講じることも考えられ、「想定外の暑さだったから、対策のしようがなかった」という言い分は通らないようにも思えます。
しかし、熱中症は、本人に自覚症状がないまま状態が悪化し、重症化すれば死に至ることも少なくありません。そのため、熱中症対策を作業員任せにして、「随時水分や塩分を摂ってください」と伝えるだけでは足りなかったといえます。
十分な熱中症対策を行っていたと評価されるためには、作業中や休憩時に、「作業開始から1時間経ったので、水分補給してください」と指導したり、水分補給を行っているかを定期的に確認したりする必要があったでしょう。また、熱中症のおそれのある作業員がいないかを適切に報告させる体制も整えておくべきでした。
したがって、こうした対策をしなかったのであれば、裁判所は、熱中症対策違反があったと判断する可能性が高いです。
熱中症対策違反があると、治療費などの賠償責任を負うことがある
熱中症対策が十分でなかったことによって、作業員が熱中症になったり、熱中症が重症化したりした場合は、それによって生じた損害を賠償する義務を負います。
本件の詳しい事情は明らかでありませんが、熱中症の治療にかかった費用や、熱中症にかかって働けなかった場合の収入相当額も賠償の対象に含まれるでしょう。
熱中症対策の方法は厚生労働省のパンフレットなどを参考にする
以上のとおり、熱中症対策が十分でないと外部業者の作業員に対しても責任を負うことがあるため、企業としては十分な熱中症対策を行うことが重要です。
また、令和7年6月1日の労働安全衛生規則の改正により、熱中症対策が義務付けられました。熱中症を生じるおそれのある作業を行うときは、必ず熱中症対策を行わなければならないため、注意が必要です。熱中症対策については、行政通達やパンフレットに説明があります。
たとえば、熱中症対策を強化する法令改正に関して、厚生労働省パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」には、服装等について「熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること」との説明があり、現場でも参考になります。
安全配慮義務については、以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。
参照: 安全配慮義務とは?根拠となる法律、違反事例や対策などを詳しく解説
【回答者:弁護士法人咲くやこの花法律事務所 弁護士・小林 允紀】
◆「釣具業界の法律相談所」の連載記事一覧はコチラ
↓ 様々なトラブル相談はコチラ ↓
・企業法務に強い弁護士への法律相談サービス「咲くやこの花法律事務所」
・顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について【大阪をはじめ全国対応可】
関連記事 → 生成AIで作成した魚のイラストを使ったポスターが訴えられた!著作権侵害は認められる?【弁護士に聞く】 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト
関連記事 → 釣り堀で多発する外国人の迷惑行為。外国人の入場を一律禁止するのは問題あり?【弁護士に聞く】 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト