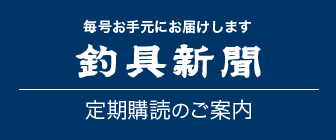早朝に現地入り、でも遊漁券売り場が見つからない…。そんな釣り人の不便を解消。スマホやPCで遊漁券が買える
早朝や夜中に現地入りする釣り人にとって、遊漁券の購入場所が見当たらず、不便を感じている釣り人は多いだろう。その問題を解決するべく、遊漁券のネット販売サービスを提供するのが今回紹介する一般社団法人クリアウォータープロジェクトだ。
同社が手がける「つりチケ」による遊漁券販売は2016年に4漁協からスタート。2017年7月に20漁協、2019年3月に43漁協と契約漁協数は順調に増加し、今年6月末時点では56漁協と契約し、51漁協の遊漁券がスマホやパソコンから簡単に購入できるまでになった。

実はこの遊漁券のネット販売サービスは、大手旅行代理店をはじめ複数の企業が取り組んできたものの、そのほとんどがこの事業から撤退している。
現在は最大手の「つりチケ」と「フィッシュパス」の2つが残っているだけだ。
この2社の大きな違いは、「つりチケ」は漁協から、「フィッシュパス」は遊漁券取扱店から遊漁券を購入するシステムになっていることだ。
利用者には大きな違いはないが、「つりチケ」は漁協の遊漁券販売所をネット上に出店する仕組みを提供し、そのネットショップで販売する商材はすべて漁協側が決定する。
日券だけのところもあれば、年券を販売する漁協もある。既存の販売店への影響もあるので、ネット販売への依存度は漁協によってさまざまだ。今のところネット販売に積極的な漁協で売上総額の20%強。まだ多くの釣り人が実店舗で購入しているといえるだろう。
漁協は販売手数料としてネット販売額の15%が必要になる。しっかりとした販路を独自で確保している漁協はその手数料がネックに感じるかもしれない。
遊漁券のネット販売が普及しなかった理由とは…?
遊漁券のネット販売は利便性が高い。だが、この事業がこれまで成立しなかったのは、ひと言でいえば「漁協との信頼関係を築けなかった」ことが大きな要因だろう。
「つりチケ」が少しずつだが契約数を増やしているのは、遊漁券を販売すること以外にさまざまな事業を提案できるプランニング力があるからに他ならない。
しっかりとパートナーシップを築いて活動している名倉川漁協(愛知県)の場合、管轄内の段戸川における渓流魚の資源管理からキャッチ&リリース区間の設置、遊漁者の管理システムの確立など、コストパフォーマンスに優れた事業プランを的確に提案している。
イベントの企画では釣り人だけでなくサポート企業を募り、渓流ルアーやテンカラ釣りなどの講習会を頻繁に開催している他、入川道の整備まで行っている。


手間はかかるが、予算をかけない提案は、現在の日本の内水面漁業にとてもマッチングしたコンサルティング業務といえるだろう。
運営改革をしたいが最初の一歩を踏み出せない中小の漁協にとっては、「つりチケ」はありがたい存在である。これから経験を積むことによってプランニング力に磨きがかかってきそうだ。
次ページ → 釣り人が活躍して釣り場を守る取り組みを紹介!