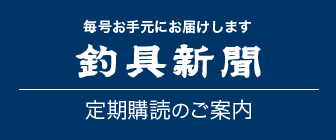漁協はあらゆる団体と連携して漁場管理をする時代


多くの漁協が組合員の高齢化や減少で運営に苦しんでいる。多額の経費支援が受けられる『やるぞ内水面漁業活性化事業』は、新規事業に取り組むうえで大きなサポートといえるだろう。
しかし、こんな素晴らしい企画が目の前にありながら、応募数は全国から35団体のみと少ない。公募から募集締め切りまでの期間が短かったこともあるが、この数字が新しい事業に手が付けられない現在の内水面漁協の現状を物語っているのかもしれない。
内水面漁業の将来を不安視する声は釣り人からも上がっている。
第一期やるぞ内水面漁業活性化事業の成果報告会において、審査員を務めた佐藤成史氏(フィッシングジャーナリスト・群馬県内水面漁場管理委員)からは、「組合存続に危機感を覚える状況下で一番影響を受けるのは釣り人。だから新しい事業をするならどんどん釣り人を使ってほしい」という提案があった。高齢化がさらに進むこれからの時代、やはり漁協が単体で積極的な事業を展開することは難しい。

その一方で、第一期の同事業に採択された団体の一つ、『京の川の恵みを活かす会』のように様々な立場の人や団体が集まり、連携して活動の幅を広げている組織もある。
同会の代表は京都大学准教授の竹門康弘氏が務め、漁協、研究者、市民、行政、NPOなどのメンバーが構成され、その活動には釣り人や学生も参加している。
天然資源を回復させるための河川整備や生息調査から、食文化の再興、シンポジウムの開催まで、その名の通り、川の恵みを豊かにして活かしていく活動をしている。これからの漁場管理の手本の一つとなる団体といえるだろう。
やるぞ内水面漁業活性化事業は令和2年度も継続されることになった。第二期募集は4月から始まり、5月8日で募集は締め切られた。
2年目ということでさらに画期的な事業が提案され、前年度を上回る応募数があることを期待したい。(第2回・了)
取材協力・情報提供のお願い
この連載企画の取材を通して画期的な釣り場づくりに取り組んでいる方々や、調査研究で成果を上げている方々とお会いできることをとても楽しみにしています。これからの1年、読者の方々と一緒に未来の漁場管理の在り方を考えるコーナーを作るべく、現場を回って取材する所存です。
読者の地元で「この釣り場の活動は素晴らしい」といった情報があれば、本紙編集部 mail@tsurigu-np.jp までご一報いただければ幸いです。よろしくお願い致します(岸裕之)。
関連記事 → 【第1回】未来に繋がる釣り場環境整備~漁業者と釣り関係者が協力して釣り場作りを~
関連記事 → 【第3回】アユルアーで新たな友釣りファン作り。釣り場次第で新たなゲームフィッシングも誕生か!?
関連記事 → 【第4回】遊漁券もネット販売の時代!?
関連記事 → 【第5回】増加するブラックバスの有効利用。各地でバス釣り人の受け入れ態勢が充実
関連記事 → 【第6回】滋賀県安曇川廣瀬漁協に見る漁場管理者のプロ意識~これからの時代の漁場管理と釣り人へのサービス考察~
関連記事 → 【第7回】スーパートラウトの聖地・長野県犀川(さいがわ)に見るニジマスの活用
関連記事 → 【第8回】貴重な資源量を誇る山梨県甲州市・日川渓谷の「野生魚育成ゾーン」