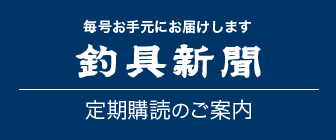淀川の天然アユは今の10倍に増やせる!

京都は関西圏の中でもアユへの思い入れが強い地域である。京都の市街地を流れる鴨川や、淀川水系の本流である宇治川はかつてアユ竿が林立するほどの友釣りファンで賑わった。
その光景は京都に夏を告げる風物詩であり、活かす会にとってアユが遡上し生息できる豊かな流域環境を取り戻すことは活動の中心となっている。
アユの遡上数は年毎にバラツキがあり、その要因を突き止め、安定した資源量を確保することは調査研究の大きな目標となっている。だからこそ産卵場の環境整備、孵化後の流下仔魚調査、河口域での生息調査、遡上数の確認まで、アユの一生を追う調査を継続している。
では、淀川水系の天然アユは今後どのぐらいまで増やすことができるのか。
竹門先生がターゲットとしている数値は、宇治川・天ヶ瀬ダム(着手1955年/竣工1964年)の建設に伴い実施された環境アセスメント(1956~1959年のダム下流域アユの生息数調査)のデータだ。この調査を実施したのは京都大学理学部動物学教室の川那部浩哉教授であり、竹門先生は後に同教授の門下生になる。

このアセス調査の結果から淀川三川の下流域のアユの生息尾数は約400万尾と推定された。大阪湾から遡上するアユの減耗率を6割強とすると当時の平均的な遡上数は約650万尾であり、2桁の変動を加味すると65万〜6500万尾になる。近年の遡上数は3万〜150万尾にとどまっており、ゼロが一つ足りない。


ただ、今後アユの成長や繁殖に必要な河川環境を改善し、海へ下ったときに外敵から身を守りやすい干潟環境を再生することができれば、天然アユの遡上数を10倍に増やすことは十分に可能であると竹門先生はいう。
もし、天然アユが今の10倍に増えたなら、淀川の河川環境整備は全国のモデルケースとなるだろう。

増加する外来種やカワウなどの捕食者が懸念材料
淀川水系ではこの10年ほどでジワジワと新たな外来種が生息域を広げている。
スモールマウスバスとアメリカナマズ(チャネルキャットフィッシュ)はラージマウスバスやブルーギルよりも流水域に適応できるため、河川に生息する在来魚の捕食者になっている。在来の魚食魚とも競合し、自然再生に取り組む淀川では大きな懸念材料になっている。
河川環境整備、この人に注目! 竹門康弘氏

京都大学准教授。宇治市にある京都大学防災研究所内に竹門研究室がある。「京の川の恵みを活かす会」の代表、賀茂川漁業協同組合理事を務める。
1957年生まれ、東京都出身、宇治市在住。築地魚河岸で仕出し屋だった祖父から魚の目利きと包丁捌きを、釣りキチだった父から竿捌きを、秋田育ちの母から山菜採りを学んだ。
故郷の多摩川で川遊びを覚え、高度成長期に荒廃する河川環境を目の当たりにした世代。自然豊かだった多摩川を知るからこそ、河川環境改善への思いが強いという。
現在、最も好きな釣りは南紀を中心とした地磯のフカセ釣り。既存の釣りスタイルにこだわらず、魚の習性に基づいた独自の攻略法で魚を仕留めるタイプ。「おいしい魚を食べたい」という思いが研究、活動、釣りのモチベーションになっているという。
<竹門先生から釣り具業界への提言>
「もっと多様な釣りの楽しみ方を提案してほしい」
今回の取材で竹門研究室へ伺った際に、釣りの楽しみ上手な研究者の視点から「釣具業界への提言」をお聞きした。
「釣り具業界は流行を追い過ぎているように思えます。コマーシャリズムで大量生産、大量消費の釣りスタイルを釣り人に押し付けているように見えるんですよ。長い目で見て、それでいいのかどうか。
例えば、ブラックバスのルアー釣り。在来魚でもルアーで釣れる魚はいるし、大物を釣りたいならスズキやヒラスズキなどの海の魚を狙えばよい。それから、同じ魚種でも各地の風土にあった地域固有の釣り方があります。日本の釣り文化はもっと発掘すれば、在来魚の釣りはまだまだ発展の余地がありますよ。もっと多様な釣りの楽しみ方を提案してほしいですね」(竹門先生談)
次ページ → 京の川の恵みを活かす会の活動を紹介!