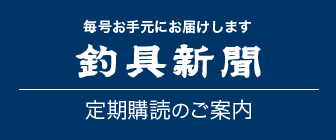山梨県北東部の小菅村(以下、村)を流れる小菅川で6月28日、釣り人、漁協、住民、釣具メーカーが連帯し、愛すべき川を未来へ繋げるイベント「こすげ・つり人ミーティング」が開かれた。
同河川下流域に導入されているC&R区間を会場にした同催しでは、小菅村漁業協同組合(以下、漁協)の古菅一芳組合長が村内での渓流魚の養殖事業や小菅川の先進的な川づくりについて講話を行うなどした。
こすげ・つり人ミーティングは、小菅川リバーキーパーで釣り人の井ケ田勝さんが主催した。井ケ田さんは「@yamametoasobu」のアカウントで、小菅川の釣りや村の情報などをSNSで発信し続けている。

ヤマメ、イワナが棲み、釣り人目線の釣り場づくりが進む小菅川。流域に住む人たちの生活にも欠かせないこの川は、文字通りかけがえのない財産。いま以上に川への関心を寄せてもらい、次世代に美しい流れを引き継いでいこうと同イベントが企画された。
活動のキーワードは「#小さな一歩が未来へ繋がる」。井ケ田さんのこのイベントについて漁協が協賛し、村の老舗旅館である廣瀬屋旅館などが協力を申し出た。
会場は小菅川の金風呂河原。平成11年からC&R区間として開設
イベント会場は、奥多摩湖のバックウォーターに近い小菅川の金風呂河原。一帯は、漁協によってフライ・ルアー・テンカラ専用のC&R区間が平成11年、全国3番目という異例の速さで開設され、シーズンを通して多くの釣り人が渓流魚との出会いを求めて足繁く通う。
この日のプログラムは、午前中に①小菅村漁協加藤源久理事の講話、②金風呂河原のゴミ拾い、ウグイ産卵場造成作業、③同河原へのニジマス成魚放流、④同漁協古菅一芳組合長の講話となり、昼食後の午後からはフライフィッシング教室などが行われた。

このうち、加藤理事と古菅組合長の講話では、参加者たちは各自用意したイスに座り聴講。真夏を思わせるような強い日差しのもと、両氏の語る小菅川の川づくりなどについて皆、熱心に聞き入った。
子供が川に来て魚が釣れないと面白くない
加藤理事は、大きく▽小菅川の概要▽遊漁料の徴収など根拠となる法令▽各漁協が実施している成魚放流▽渓流釣りの素晴らしさの4つのテーマで話した。
小菅川は、全長138㎞ある多摩川の源流部を構成する支流の一つ。大菩薩峠の北側が水源で、概ね魚が生息できる範囲で17㎞の流程を持つ。ただ、17㎞のほぼ全域について堰堤、護岸など人工構造物が設けられているとした。

加藤理事は、小菅川の東部地区では昭和50年から約15年間、業者によって川砂利の採取が行われ、それが一段落した頃、当時の田中角栄氏の日本列島改造論もあり、公共事業の名のもと土木工事が盛んになったこと。事業の推進により、平成時代の中頃まで河川の随所に護岸が整備されたことなどについて解説。
同理事は、「その頃の護岸は、ブロック積みで苔も生えない。現在は自然石で整備し、苔が自生するような護岸になっているが、これは河川法が20年ほど前に改正されたから。それよりも前は、できるだけ早く上流から下流へ水を流すということを河川工事の第一にしていた。一直線になった河川は植物も生えないし、石もないので生き物が棲めない」などと指摘した。
多摩川の上流部を堰き止め、昭和32年に満水となった奥多摩湖。加藤理事は同ダム完成前、小菅川に生息していた魚種はイワナ、ヤマメ、アブラハヤ、カジカ、ウグイと東京湾から遡上してきたウナギの6種類。が、現在はアユ、ハス、カワムツ、ナマズ、ブラックバス、フナ、モツゴ、モロコ、ヌマチチブ、ヨシノボリの仲間、シマドジョウなど15種類ほど確認しているとした。
同理事はさらに、釣り人の河川へのゴミの投げ捨てにも言及。C&R区間を導入した25年前と比べると、河原のゴミは減少傾向だが、近年はルアー用の釣り糸、タバコの吸い殻などが捨てられていると指摘。が、「河原に落ちているゴミを、率先して回収する釣り人が増えてきている」とも述べ、モラルを重視する釣り人が顕在化していることを喜んだ。
子どもたちが川にきて魚が釣れないと面白くないとも語り、「全域を基本C&Rにするか、魚を持ち帰りたい場合は、例えば5尾までなど制限尾数を設ければ、子どもたちが来てもいつでも釣れる釣り場になる」と持論を展開。「いつも魚がいる川になるような取り組みを、皆でできれば」と締め括った。
ゴミ拾いとウグイの産卵場の整備、ニジマス放流も実施
参加者はこの後、ビニール袋を手に周辺のごみ拾い、加藤理事の指導を受けながら、ウグイの産卵場をC&R区間に2カ所整備した。産卵場については、河原にあるソフトボール大ほどの苔の付着していない石を水通しの良好な瀬に約1.5m~約2m四方程度の広さで敷き詰めるもの。参加者は流れに立ち込んで造成した。
続けて、漁協によるC&R区間へのニジマス(多摩源流ニジマス)放流を手伝った後、古菅組合長によるレクチャーに移行。同組合長は、小菅川の歴史や漁協の水産庁長官賞受賞経緯などについて語った。

漁協は昭和25年頃に発足。小菅川にはヤマメが自然繁殖し、釣り客が増加してきた中、昭和36年に村民の酒井巖氏(故人)が国内では民間で初めてというヤマメの人工養殖に成功する快挙を成し遂げる。以降、村ではヤマメの生産量が昭和40年代頃に増加していったという。
村では、ニジマスの養殖がそれよりも前の昭和27年から始まった。古菅組合長は、「私の父親は冷水を入れた木箱をバイクに括り付け、生きたニジマスを配達していた」とのエピソードを披露。当初、村の養魚場は3軒だったが、ピーク時には副業含めて7軒にまで増加、日夜、渓流魚を生産していたという。
甲信越では初の試みのC&R区間開設の経緯についても古菅組合長は触れ、「テンカラ名人の堀江渓愚さん(故人)が小菅川に訪れていて、C&R区間を設定してみてはどうかと促された」と説明した。
河川のゾーニングに早くから取り組む
漁協の特色は、小菅川にこの「C&R区間」を始め、「尾数制限区」「永年禁漁区」「冬期ニジマス釣り場」など河川をゾーニングしている点。古菅組合長は「川の使い分けということで、国内河川漁協の中でも早い段階で本格的に取り組んだ」と強調した。小菅川の尾数制限区は、1日に釣り人が釣っても良い魚の数を5尾までと定めたエリアで、漁協は同区域を本流上流部に位置付けている。
尾数制限で釣り上げる魚の数を規制している上流部だが、漁協は宮川や玉川などの支流については永年禁漁区に設定した。同区は、放流を一切せずに地の魚を保護するところ。
同組合長は「出水すると、支流にいた天然魚も本流に出てくる。だから、本流でもすべて放流した魚ではなく、自然繁殖した魚も当然のように釣れる」と、小菅川本流では偏向することなく魚が釣れることを説いた。
魚族保護とともに、釣り人が望む釣り場運営を同一歩調で実践する漁協へのファンは多い。年間を通して首都圏を中心に大勢の釣り人が訪れ、地域における経済活動の活性化にも大きく貢献している。
漁協は昨年11月、大分県で開催された「第43回全国豊かな海づくり大会」で、海がない山梨県の団体では初の水産庁長官賞を受賞した。フィールドを使い分けての魚族資源保護、年間を通して渓流釣りが楽しめるといった取り組みが高く評価されてのものだ。
古菅組合長は、講話の中で「水産庁長官賞受賞は、村の漁協関係者だけではなく、村民、ここにいらっしゃる皆さんのように小菅に足を運んでいただいている方々のおかげ」と謝意を示し、「漁協は小さい組織だが、多くの皆さんに来ていただき、さらに交流人口が増えることを願う」と念願した。
養殖業が盛んな村だが、同組合長は村内で養殖した魚について「多摩源流」(特許取得済み)というネーミングで出荷していることも特徴の一つだとした。関連して食味にも話題が及び、「小菅の魚は水温の変化に強く、身が締まって美味しい。手前みそだが、他の魚と比べて味が違う」と胸を張った。
メーカーブースやフライフィッシング教室も

古菅組合長の講話で午前の部のプログラムは終了。参加者は昼食後、出店各社のブースを巡ったり、フライフィッシング教室を受講するなどして、野外イベントを堪能した。
今回のこすげ・つり人ミーティングには、Foxfire(フライラインのブレスレット作り、国産熊スプレー「熊一目散」の試射・販売など)、すれ鱒屋(コマーシャルフライの展示販売、フライフィッシング教室)、handmade4stream(鱒のブローチ・オブジェ)、ネルエピック(ネルエピック商品展示体験など)FFラボ(フライフィッシンググッズの紹介・販売)などのメーカーがブースを出店したほか、「道の駅こすげ」のスパイスカリー店のマサラジェイコがスパイスカリーを販売した。 【小島満也】
関連記事 → アユルアーの基本、要点教えます!上州屋とウイストが体験教室を開催。ウイスト社の袖山氏、冨柗氏が直々に指導 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト
関連記事 → 入間川の本流にオイカワの産卵床を設置。豊かな水辺を目指して【日本釣振興会 埼玉県支部】 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト