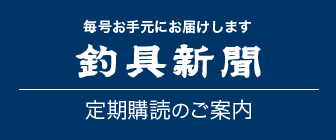釣りエサのスペシャリスト・長岡寛さんの連載「お魚さんッ、私のエサに食いついて!」です。釣りエサに関する事以外にも魚の生態や環境など様々な内容を紹介します。
今回は、オオクチバスの嗜好性等について解説して頂きました。

世間では広く呼ばれている「ブラックバス」というのは俗称で、分類上ではスズキ目、スズキ亜目、サンフィッシュ科、オオクチバス属という位置付けになっています。バス釣りのファンにとっては釈迦に説法となってしまいますが、日本で言うバスはほとんどがオオクチバス(ノーザン・ラージマウスバス)を指しています。

ご存じの通り1925年に実業家の赤星鉄馬氏がアメリカのフロリダ州から持ち帰り、神奈川県の芦ノ湖に放流されたのが最初とされています。
日本では冒頭で挙げたオオクチバスやコクチバスが特定外来種として指定されています。
これらを含む特定外来種の扱いについては2005年6月に施行された「外来生物法」によりオオクチバスとコクチバスの輸入、飼養、運搬、移植を原則として禁止することとなっています。 その利用方法についてはまだまだ議論の余地があるかと思いますが、それについてここでは触れずに、オオクチバスに関する嗜好性など、いつものスタイルでお話しさせていただきます。
オオクチバスに関する嗜好性
オオクチバスがルアーフィッシングのターゲットとして絶大な人気がある理由は、何と言ってもその食性にあります。小魚だけでなくカエル、ザリガニ、エビ、ミミズなど動く物に対して極めて俊敏な反応を示すため活性が高ければすぐに食いついてきます。
私が初めてオオクチバスを釣り上げたのは中学2年生の時で、その頃はまだ都内の公園の池で釣りが出来たころのことです。
またさきほどの「特定外来生物法」が施行される前は、水槽でも飼育していて、餌を投入すると瞬時に食い込んでいたことが印象に残っています。
ところが、何でも瞬時に飲み込んでしまうのかというと実は決してそうではありません。その当時、プラスティックワーム(ソフトルアー)を誤飲したニジマスの消化管内にそれが排出されない状態で滞留することにより消化管に詰まってしまい、結果として斃死が起きることが問題視されていて、水中で分解する素材の開発に取り組んでいました。
水中で分解する素材の開発に着手するが…
ラージマウスバスがいる水槽にソフトルアーを投入すると、先ほどの通り瞬時に飲み込むのですが、すぐに吐き出してしまいます。
次に同じソフトルアーを投入すると学習しているらしく、チラッと見はするものの、飲み込むという動作は起こしません。一方ニジマスは何度行っても完全に飲み込んでしまいました。こうしたことからラージマウスバスの学習能力の高さが伺えます。
そして興味深いことに、ラージマウスバスはアミノ酸などを配合した素材に対しては、強い摂餌性を示していましたので、味覚についても発達しているのではないかと察しています。