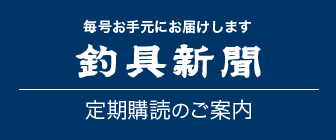ヘラブナのルーツとは…?
淡水魚のターゲットとして人気の高いお魚さんの1つにヘラブナが挙げられます。
磯釣りや渓流釣りとは異なり、水辺に腰かけてウキを見つめているヘラブナ釣り師の姿を傍から見ていると、なんと退屈そうな(語弊があるかもしれませんが…)釣りなのだろう、という印象を持たれる方もいるかもしれません。
しかし、一度あの繊細なウキの動きを見てしまうと、いつの間にか周囲のことが気にならない、独特の世界へと引きずり込まれてしまいます。

ご存じの通り、ヘラブナの原種は琵琶湖とそれに繋がる淀川水系の一部に生息している「ゲンゴロウブナ」と呼ばれる日本の固有種です。
明治時代の末期に河内地方の養殖家、橋本福松という人が、琵琶湖から淀川に通ずる水系にあった巨椋池(現在は宅地になり消滅)でゲンゴロウブナを捕まえて持ち帰り密かに養殖していました。
マブナよりも非常に大型に成長するため京都の料亭に販売していたところ、やがて人々の知るところとなったのです。
ゲンゴロウブナは、かつて農業用のため池が多くあった河内地方で盛んに養殖されたため、後に眞田忠吉氏等が中心になってカワチブナと命名されました。
当時、カワチブナは食用として養殖されていて、それまで多く養殖されていたコイと比較して、人工的な飼料を与えなくてもそこに発生する植物性プランクトンを主食としているため生産コストが低く抑えられるという利点があります。
実はこのお魚さんが植物性プランクトンを主食としていることが、ヘラブナ釣りを面白く、奥深くしている根幹にもなっています。
カワチブナが釣りの対象魚として初めて関東に移植されたのは、昭和初期で大田区にあった釣り堀「小池園」です(現在は閉鎖されています)。
当時は「関西からきた大きなフナが釣れる」ということで、大変な評判になりましたが、現在のような活魚輸送のトラックが無い時代でしたから、貨車に積んで30時間以上もかけて輸送していましたので、相当な苦労があったことは想像に難く無いでしょう。
大阪府淡水試験場(現・独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所生物多様性センター)では昭和35年から5年間に渡り、東京都釣魚連盟や日本ヘラ研の協力を得て東京と周辺の各地に放流事業を行ったほか、昭和40年からは大阪府淡水漁業協同組合では大阪府淡水試験場の協力を得て、全国各地の釣り場にカワチブナの卵を出荷しました。
こうして放流されたお魚さんがヘラブナとして多くの愛好者に親しまれるようになっていったのです。
体高ある美しい姿には理由がある
日本で見られるフナの仲間は、キンブナ、ギンブナ、ナガフナ、ニゴロブナ、そしてゲンゴロウブナの5種類です。
そしてヘラブナは先ほどお話しした、巨椋池で捕獲したゲンゴロウブナを河内地方のため池で養殖し、成長した個体の中から特に体高のある形の良いものを選別して交配させ、それを何世代も重ねて品種改良されたお魚さんです。
ギンブナの中にも体高のあるものも多く見られますし、ヨーロッパ産やシベリア産のフナの中にもヘラブナのように体高のある種類がいますが、ヘラブナは外観だけでなく、体の構造が他のフナの仲間とは大きく異なっています。
数ある特徴の中に腸の構造が挙げられます。

出典:加福竹一郎 カワチブナの起源についての一考察
ヘラブナの腸はほかのフナの仲間とは比較にならないほど長く、複雑な巻き方をしています。これは冒頭にお話しした植物性プランクトンを主食にしていることと大きな関係があります。
植物性プランクトンは動物と違って細胞壁というとても硬い殻に覆われています。そのため水中で取り込んだ植物性プランクトンを消化吸収するためには長い腸が必用なのです。
ヘラブナのあの独特の体高がある美しい姿は、その長い腸を効率よく体に収めるために進化したものと考えられます。
そしてもう1つ挙げておきたい特徴は、鰓耙(さいは)と呼ばれる水中の餌を濾し取るための器官です。

鰓耙については以前お話ししましたので詳細については割愛させていただきますが、やはりヘラブナは他のフナ類と鰓耙の数が圧倒的に異なっています。
ヘラブナは鰓耙の数が格別に多いことが他のフナ類では決して取り込むことが出来ない水中の微細な植物性プランクトンを消化管に取り込むことを可能にしているのです。

ヘラブナは水中の植物性プランクトンを主食としていることから、基本的には固形物をそのまま飲み込むことはありません。
他のお魚さんの多くは、釣り餌をそのまま吸い込む或いは飲み込んでくれるため、アタリがあればかなりの確率でヒットするのですが、ヘラブナだけはそうは行かないのです。
ヘラブナの釣りが難しいのはこれが大きな理由になっています。
次回は何故ヘラブナ釣りがこんなにも面白いのか、その理由について若干生態的な要素も含めてお話しさせていただきます。
関連記事 → ヘラブナの視覚、嗅覚、聴覚はどのぐらい?独特な魅力を放つ「ヘラブナを知る」【後編】 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト
長岡寛さんの記事 → 長岡寛 | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト
関連記事 → 匂いの強いエサって効果があるの?強烈な匂いのサナギで実験、驚くべき結果とは…? | 釣具新聞 | 釣具業界の業界紙 | 公式ニュースサイト